この連載ブログは、「あなたの人生、そしてあなたの会社の『ブランド』を、本にしませんか?」という提案のもと、あなたの中にある「遺産」(経験、知見、価値観、想い)を、あなただけの「一冊の本」として、未来へ遺すためのお手伝いをする全30回のシリーズです。「本」という形を通して、あなたの人生、そしてあなたの会社の「ブランド」を、より豊かに、そして後世に伝えていきましょう。今回は第2部、第12回目です。(過去記事:第1回 / 第2回 / 第3回 / 第4回 / 第5回 / 第6回 / 第7回 / 第8回 / 第9回 / 第10回 / 第11回)
— — — — — — — — —
『あなたの人生を、最高傑作に。~人生を編集し、未来へ遺す30のヒント~』
第1部:あなたの中に眠る「遺産」を発見する(1〜5回)
第2部:自分史を編み、未来へ遺す(6〜15回)
第3部:ブランドストーリーを紡ぎ、未来へ繋ぐ(16〜25回)
第4部:「本」が繋ぐ、過去・現在・未来(26〜30回)
【 今回は第2部の12回目です 】
自分史を「本」という形に――手にとって感じる喜びと未来への贈り物
自分だけの一冊を形にする意義
前回は、写真や資料で自分史を彩る方法をご紹介しました。今回のテーマは、いよいよ「本」に仕立てることの魅力です。古くは写本の時代から、人は大切な記録を紙に刻み、その手触り感を大事にしてきました。デジタル全盛の現代においても、その風合いと存在感は、どこか特別な安心感を与えてくれます。あなたの人生を一冊に綴り、形に残す――そのプロセスが持つ意味を、改めて掘り下げてみましょう。

自分史を「本」にするメリット
自分史を本として編み上げることには、さまざまなメリットがあります。ここでは代表的な3つを挙げながら、それぞれのポイントを掘り下げます。
永続性と保存性
紙の手触りと視覚的なインパクトは、デジタルにはない“物理的な存在感”を持ちます。
・長期保存のしやすさ
たとえ数十年後でも、開いて読むだけで当時の空気や思い出がよみがえります。電子データが読み込めなくなるリスクを考えると、紙の安心感は依然として侮れません。
・本棚に並ぶ満足感
ふと目に入る背表紙が、あなたの物語をそっと主張してくれます。デジタルデータと違って、「そこにある」ことが一目でわかることの価値は、意外と大きなものです。
特別な達成感
「本にまとめる」と聞くだけで、思わず背筋が伸びる方もいるのではないでしょうか。
・“1冊の作品”としての重み
原稿データやプリントアウトの束が、オリジナル装丁を施した本になる瞬間は、言葉にできない喜びをもたらします。
・人生を認めるプロセス
ページをめくるたびに「自分はこんな人生を歩んできたんだ」と、改めて自分を肯定できるのが“本”の不思議な力です。
家族や友人への贈り物
一冊の本として完成した自分史は、読む人の心を動かします。
・感動的なプレゼント
ありきたりな品物ではなく、あなたの人生そのものを贈る――。これは、相手にとっても忘れがたい贈り物になるはずです。
・世代を超えるメッセージ
子や孫、まだ見ぬ未来の子孫に、あなたの物語を手渡せるのは紙媒体ならではの醍醐味。そうして受け継がれていく歴史の深みは、本だからこそ生まれるものです。
製本プロセスの楽しみ
自費出版やオンデマンド印刷の発達によって、自分史を製本するハードルは確実に下がりました。にもかかわらず、実際に「本にする」となると少し大がかりな印象がありますよね。でも一方で、その“大がかりな”プロセスこそが、創造的な喜びにあふれているのです。
デザインを選ぶ
・表紙や紙質へのこだわり
光沢のある紙にするのか、クラシックな厚紙を使うのか。あるいはモノクロで統一するのか、カラフルなイラストを加えるのか。加工はどうするか――こうした選択が、あなたらしさを本に吹き込みます。
・レイアウトの工夫
写真と文章の配置をどうするか、フォントや文字の大きさ、刷り色はどうするか。誌面には数多くのディテールが詰まっていて、しかもそこに「正解」はありません。だからこそ、大変であり、面白さがあるのです。

プロの手を借りる
・製本業者やデザイナーのサポート
業者やプロのデザイナーが提案してくれる装丁やレイアウトは、想像以上に洗練されたものが多いです。
・DIY派でも可能
自分のペースで作り上げたい方は、フォトブックを作る感覚でレイアウトソフトを使うのも手。必要に応じて専門家に相談すれば、クオリティを一段上のものにできます。
自分史の価値を次世代へ
本という形でまとめられたあなたの人生は、あなた一人の記録にとどまりません。
・家族の絆を深めるきっかけになる
家族みんなでテーブルを囲み、ページをめくりながら思い出を語り合う――そうした光景を想像するだけで、温かな気持ちになりませんか? 本を中心に自然と会話が広がっていくのは、紙の力がなせる技ともいえます。
・学びの源になる
あなたが乗り越えた挫折や思いがけない成功体験は、未来の誰かにとっては大きなヒントになる可能性があります。「あの人の人生に、こんな一幕があったんだ」と、励まされる人がきっといるはずです。
特別な一冊を未来に届ける
自分史を「本」という形に仕上げるということは、あなた自身の人生をひとつの作品として確立すること。ページをめくる行為を通じ、読む側はあなたの歩みを追体験し、未来に受け継いでいく喜びを感じるでしょう。これは自己満足では終わらない、人と人とをつなげる尊い手段といえるのです。
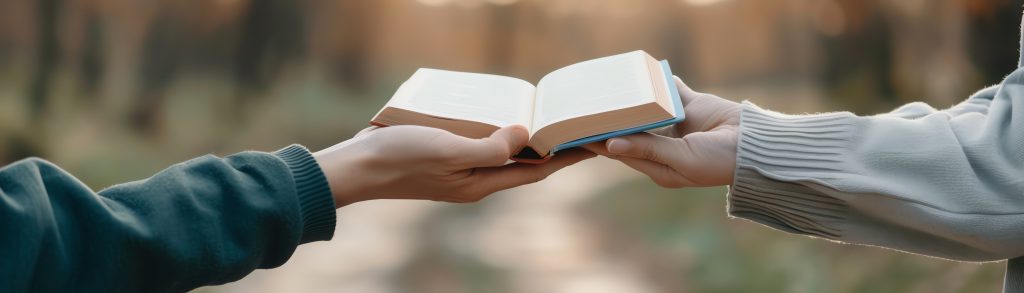
次回は、自分史の新しい「カタチ」としてデジタル技術を活用する方法をご紹介します。紙媒体と併用することで、より多くの人に、より長くあなたの物語を届けられる――その可能性について取り上げます。
— — — — — — — — —
▶︎ 次回の記事:【新連載/第13回】 デジタルで出版する新しいかたちを考える
▶︎ 前回の記事:【新連載/第11回】 写真と資料で彩る、あなたの自分史――思い出を鮮やかに伝えるヒント
▶︎ 前々回の記事:【新連載/第10回】 読み手の心に響くストーリーテリング技術
【編集余話】
自分史を「本」にするというと、一見ハードルが高そうに感じる方もいるかもしれません。でも、歴史を振り返ると、意外に「自費出版」や「小規模出版」がきっかけで世に出た名作が少なくないようです。
たとえば、子ども向け絵本の世界的ベストセラー『ピーターラビット』は、作者のビアトリクス・ポターが自費出版で世に送り出したのが始まりでした。出版社に断られ続けた彼女が自力で印刷し、知人や家族に配ったのが作品誕生の第一歩だったそうです。
もちろん多くの人はベストセラーを狙うわけではなく、“自分史”として家族や身近な方に読んでもらえれば十分かもしれません。それでも、「自分で本を作ってみる」という行為には、ちょっとしたロマンがあるもの。もし自分の人生をまとめた一冊が、未来の誰かにとって特別な出会いになるかもしれない――そう考えると、なんだかワクワクしてきますよね。
(田中)








